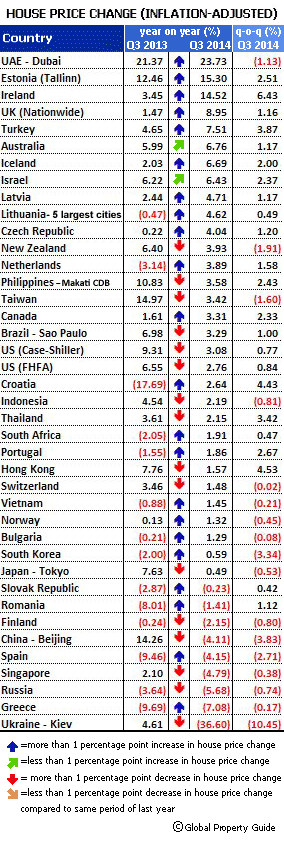オーストラリアの著名な不動産投資コンサルタントYardney氏が、これから不動産投資を行う人が避けるべき4点についてコメントしています。
以下に、海外からの投資という観点で筆者の解釈を加えながら紹介したいと思います。
1.感情に基づいて物件を買うこと
これは、自分が住んでいる地域で買う、自分が気に入った観光地やリゾート地で買うことが含まれます。
採算度外視で自分が住むためなら構わないでしょう。しかし投資として考えると、これらはデータを分析し、将来性を考慮した投資判断に基づくものではなく、何となく近くで安心できるとか、他の人も自分と同じものを好むはずという感情に基づくものです。
自宅の近くのほうが、海外の成長都市で平均的な物件を買うのに比べ、より成長性の高い地区・物件を的確に選ぶことができるという判断なら良いと思います。
例えば、自分の住んでいる都市(または国内都市)の成長率が平均3%、ある海外都市の成長率が平均5%とします。
自分の住んでいる都市については見識があるため、ピンポイントで平均を上回る6%の成長が見込める物件を探せるということであれば、あえて地元で投資する意義があるでしょう。
しかし、自分の住んでいる地域の将来性が基本的に下り坂なのであれば、これから上り坂が続く都市で、その中でも成長性の高い地区、適切な物件を選べるように勉強し、努力するほうが賢明と考えます。
海外で投資する場合でも、旅行で行ったことがあるとか、日本語での情報が用意されているということで、観光地・リゾート地を選好していないか注意が必要です。先にも触れましたが、投資でなく、採算度外視で自分が住むためなら別です。
2.計画性がないこと
(1)投資に踏み切れない
十分に勉強してから、調査してから、もっと値段が下がったら買おうと考える人も大勢います。
しかし、完全に条件がそろうことはありません。完全な条件がそろうのを待っている人は、仮にそれが本当に来ても、もっと良くなる状況を待ってしまい、結局は動けないでしょう。
確かに、全く勉強せずに、業者の言うままでは1件目の投資でアウトになってしまい、次に進めないリスクがあります。
全く勉強しないのは論外ですが、少なくとも修復不能な失敗をするおそれがない程度まで学んだ後は、投資しながらさらに学んでいく、仮に間違えても次の投資機会で活用するという姿勢でないと、チャンスを逃してしまいます。
(2)十分な投資をしない
せっかく不動産を購入しても、そのローンの返済だけに集中してしまう人もいます。確かに残債が減っていくと安心ですし、支払う金利が少なくなるのも事実ですが、レバレッジを利かせた資金活用の面では非効率とも言えます。
ローンの返済を行えば安全性は高まりますが、一方で、さらに不動産を購入し資産ベースを拡大する可能性を制限することにもつながります。
返済に余裕があるなら、余った資金を次の物件の頭金にしたり、既存物件の値上がり分を抵当に入れて次の物件購入の頭金を調達する戦略も考えられます。
ローンの返済に使った資金は金利を減らすことにしかなりませんが、ローン返済の代わりに次の物件に投資した場合は、さらなるキャピタルゲインを狙うこともできます。
もちろん、無闇に物件数を増やすと返済に行き詰るリスクも高まりますので、資金管理が必要です。
(3)投資額が多すぎる
確かに、物件の価格上昇が続く限り、できるだけレバレッジを掛けた方が資産は増えていきます。一方で、値下がりすると加速度的に資産が減少していきます。
また、あまりローン額を大きくしてしまうと、家賃が下がったり空室が出たときに、返済に行き詰るかもしれません。
悪いことがいくつか重なってもローンの返済が続けられるように、また、一時的に価格が下がっても次の値上がり局面まで待てるように、堅実な計画が必要です。
3.投資ポートフォリオの見直しをしない
海外不動産投資の場合、主な狙いはキャピタルゲインです。街の成長に投資しているのですから、長期投資が基本です。
ただし、狙った収益が上がっていない物件で、将来の好転も見込めない場合、資産の入れ替えも考える必要があります。
この地区が発展すると見込んで買ったものの、他の地区のほうが発展していて当面それが続きそうだ、政府もそちらに重点的にインフラ投資をしているというケースもあるでしょう。
確かに、物件の入れ替えには株式投資に比べればコストがかかります。しかし、そのコストを惜しんで低成長を甘受してしまうと、長期的には大きなリターンの差が開いてしまいます。
例えば、価格上昇率が年3%の物件と、年6%の物件があったとします。
最初に1億円を投資した場合、10年後、前者は1.34億円に、後者は1.79億円の資産に成長しています。20年後は、前者は1.81億円、後者は3.21億円と、資産価値に相当な違いが出てきます。(同様の状況が、シドニーでは過去20年間で実際に起こりました)
資産入れ替えに伴う少々のコストと手間を惜しんでしまうと、将来の可能性を摘んでしまうリスクがあります。自分の老後の選択肢や、子孫に手渡せる資産のことを考えると大きな違いです。
4.リスク管理をしない
人口が増え続けているといっても、不動産の価格が下がらないとは限りません。
長期的には人口動態、所得水準が利いてきますが、短期的には、金融機関の融資姿勢、金利動向、新規物件の供給と需要バランスに大きく左右されます。
長期的には値上がりが期待できるとしても、一時的に値下がり、空室の発生、金利の上昇、場合によっては失業期間にも備える必要があります。
不運が重なってローンが払えなくなると、物件の売却を余儀なくされます。売り急ぎとなりますので不利な価格となる可能性が高まりますし、何よりもそのまま保有していれば得たであろう将来のキャピタルゲインを失うこととなります。
融資を受ける際に、海外の銀行であれば標準的なオフセット・アカウント、ライン・オブ・クレジットを設定し、いざというときでも資金を引き出し、当面凌げるようにあらかじめ備えておくことが大切です。
結局は、いざというときに当面必要となる現金を用意できるかどうかに行きつくと思われます。預金として置いておくか、追加で借りられるように事前に銀行と契約しておくかです。
なお、通常、預金金利よりもローン金利のほうが高いため、どうせ現金を置いておくのであれば、ローン額と相殺されるオフセット・アカウントを持つことが推奨されています。預金金利には所得税もかかるので尚更です。
また、リスク管理としては、医師、弁護士、企業経営者など、職務に関して多額の損害賠償請求を起こされる可能性がある場合、誰の名義で購入するかも留意が必要とされています。
損害賠償の制度が日本と英米法では異なりますので、日本ではそれほど神経質でないかもしれません。英米法では、懲罰的損害賠償の制度があり、実際の損害額とは別に、(悪意、重過失等の場合)ある種の制裁として高額の賠償金が課せられるケースもあります。
このため、家族を受益者とするTrust(財団法人のようなもの)を設立し、この団体名義で不動産を取得するケースは珍しくありません。もっとも、設立、維持にもコストがかかりますので、所有物件数が一つ二つの一般個人投資家の場合は、通常そこまではしていません。
この点は、日本の不動産投資でも、個人名義と法人名義のどちらが良いかという議論に通じるところがあります。