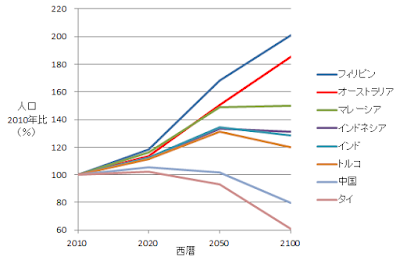以下は、豪主要都市ごとに、5年、10年、15年のスパンで見た住宅価格の年間上昇率です。実質価格ですので、物価上昇分は差し引かれています。
Source: PropertyUpdate.com.au
直近5年間(黒のグラフ)で見ると、シドニーが年4.5%と突出しています。物価上昇分(年率2~3%)も加味すると、数値の上での住宅価格は年平均6.5~7.5%のペースで上昇したことになります。
他都市を見るとマイナス圏に沈んでいるものもあり、直近5年間の動きは都市によってまちまちであることが分かります。(物価上昇分を差し引いてマイナスとなっていますので、名目値の価格は概ね横ばいです)
直近10年間(赤のグラフ)で見ても、まだバラつきが見られます。
直近15年間(青のグラフ)で見て、ようやく各都市の上昇率が概ね同水準にならされています。
15年のスパンで見ると、シドニーの上昇率は最下位水準です。この点を捉えて、ここ3年間のシドニー・ブームも、過去の出遅れを取り戻したまでで、バブルではないと言われています。
15年のスパンで見ると、シドニーの上昇率は最下位水準です。この点を捉えて、ここ3年間のシドニー・ブームも、過去の出遅れを取り戻したまでで、バブルではないと言われています。
また、ブリスベン、パースなど、この5年間でマイナス圏に沈んでいる都市でも、15年のスパンで見れば大きく伸びているものもあります。つまり、過去、別の時期に大きく伸びたということです。
一方、例えば、10年前にシドニーで物件を購入したものの、期待したほど価格が上昇しないので5年前に売却したという投資家の場合、直近の大幅な価格上昇を享受できていません。取引コストの分、損失が発生していた可能性もあります。
一方、例えば、10年前にシドニーで物件を購入したものの、期待したほど価格が上昇しないので5年前に売却したという投資家の場合、直近の大幅な価格上昇を享受できていません。取引コストの分、損失が発生していた可能性もあります。
短期で見れば、これからどの都市が伸びるか、より緻密な見極めが必要です。
もっとも、「理屈の上では、こうなりそうだ」ということは言えますが、過去の事例を見ても、専門家でも予想を外しています。
不動産業界、金融業界の多くの専門家が、「シドニー相場はもう終わり。次はブリスベンだ」と2年近く(現在も)言い続けています。過去3年間でシドニー住宅価格が40%も上昇するとは、誰も予想できていません。20%ほど上昇したところで上手く売り抜けたと考えていた投資家は、今、悔しい思いをしているかもしれません。
1000万円の自己資金で5000万円のマンションを購入し、6000万円で売れた(譲渡益1000万円)というのもなかなかの利益ですが、あと一年半保有を続けていれば、7000万円で売れた(譲渡益2000万円)というのが、直近3年のシドニーの市況です。
もっとも、「理屈の上では、こうなりそうだ」ということは言えますが、過去の事例を見ても、専門家でも予想を外しています。
不動産業界、金融業界の多くの専門家が、「シドニー相場はもう終わり。次はブリスベンだ」と2年近く(現在も)言い続けています。過去3年間でシドニー住宅価格が40%も上昇するとは、誰も予想できていません。20%ほど上昇したところで上手く売り抜けたと考えていた投資家は、今、悔しい思いをしているかもしれません。
1000万円の自己資金で5000万円のマンションを購入し、6000万円で売れた(譲渡益1000万円)というのもなかなかの利益ですが、あと一年半保有を続けていれば、7000万円で売れた(譲渡益2000万円)というのが、直近3年のシドニーの市況です。
一方、10年~15年の長いスパンで見れば、どの都市に投資していたとしても、概ね年5%程度の価格上昇を享受できたと言えます。物価調整前の数値であれば、年7~8%の価格上昇となります。
5年程度の期間で投資した場合は当たりはずれがあると言えます。一方、15年程度の期間であれば、一時的にマイナスになる時期もあるかもしれませんが、概ね安定した収益を得られそうだと言えます。
売買のたびに各種手数料、税金もかかりますし、何より、海外での不動産投資は都市の成長、人口増加に賭けているのですから、長期での投資をお勧めしたいと思います。
家賃収入の利回りも、日本と比べ、当初は低めかもしれませんが、物価上昇、所得増、人口増で中長期的には上昇圧力がかかります。最初に投じた資金との関係で言えば、家賃からの利回りは基本的に上昇を続けます。基本的に家賃の下落を見込む必要がある日本の不動産投資とは、この点が大きな違いです。
5年程度の期間で投資した場合は当たりはずれがあると言えます。一方、15年程度の期間であれば、一時的にマイナスになる時期もあるかもしれませんが、概ね安定した収益を得られそうだと言えます。
売買のたびに各種手数料、税金もかかりますし、何より、海外での不動産投資は都市の成長、人口増加に賭けているのですから、長期での投資をお勧めしたいと思います。
家賃収入の利回りも、日本と比べ、当初は低めかもしれませんが、物価上昇、所得増、人口増で中長期的には上昇圧力がかかります。最初に投じた資金との関係で言えば、家賃からの利回りは基本的に上昇を続けます。基本的に家賃の下落を見込む必要がある日本の不動産投資とは、この点が大きな違いです。
なお、ローンを組んでレバレッジを利かせる場合は、物価の上昇分も影響があります。総じて、物価の上昇に伴い、賃金水準も上昇し、物件価格(地価、建築コスト)や家賃も上昇していくと考えられます。
(景気や需給関係にも左右されますので、短期ではそうならないこともあります)
見た目のローン元本はほとんど減っていないとしても、物価上昇率分、毎年元本の価値が目減りしているようなものです。
一方、中長期で見れば、家賃収入は上昇傾向にあり、時間の経過とともに返済は楽になっていきます。(ただし、急激な金利上昇による、一時的なショックに耐えられる備えは必要です。政府の政策しだいで金利は即日上がることもありますが、家賃はすぐには増額できません)
逆に、豪ドル預金をしている方は、この元本の目減り効果がマイナスに働きます。金利として受け取った分を全部使ってしまわないよう注意が必要です。