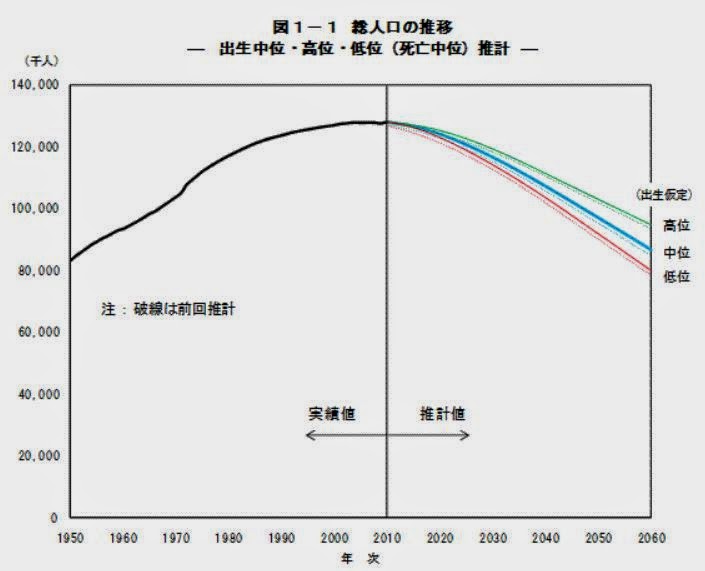オーストラリアは広大なため、不動産投資と言っても、どこで買えば良いかよく分からないと感じるかもしれません。
オーストラリアの人口と経済活動は、沿岸部に集中しています。将来の住宅需要、それから物件管理の利便性を考えれば、こうしたエリアを選ぶのが鉄則です。
下図の赤い部分だけで、オーストラリアの経済活動の8割を占めています。これだけでも対象がかなり限定されていることがお分かり頂けると思います。
Source: Grattan Institute
さらに、各主要都市の中でも、経済活動の中心地がはっきりしています。下図は、上から順に、シドニー、メルボルン、ブリズベンです。
Source: Grattan Institute
雇用の量は経済活動の多い場所に集中しますので、このエリアへの通勤の便を考慮することは大切です。シドニーでは、通勤時間帯の慢性的な渋滞のため、人気エリアが、緑豊かな郊外から、市の中心に近いエリアへと移りました。このトレンドの変化は、ここ10年~20年の住宅価格にも影響を及ぼしています。
また、こうした経済活動の中心地周辺に、店舗、レストラン、カフェなども集まります。さらに、こうした地区に対しては、州政府や市役所も社会インフラ整備に手厚く投資します。
特に、インフラ整備については、政府が税金を使って、自分の不動産の価値を挙げてくれるようなものです。
もっとも、不動産の価格、家賃の動向は、需要と供給のバランスに左右されます。たとえ経済活動の中心地で需要が多くても、タワーマンションが次々にできるなど、需要以上に供給が多ければ値上がりは期待できません。
経済活動の中心地までのアクセスが良いことに加えて、建築規制や物理的な土地不足のために新規供給が限定されている地区が狙い目です。都市の規模が拡大していく中、こうした地区はますます貴重性が高まります。
現在の都市圏人口は、シドニー、メルボルンは約400万人、ブリズベンは約200万人です。豪政府統計省は、2050年にはこの人口が2倍になると予測しています。
将来、(東京に例えれば)千代田区、港区、渋谷区の高級住宅街のようになりそうな地区を、今のうちに押さえておくということです。