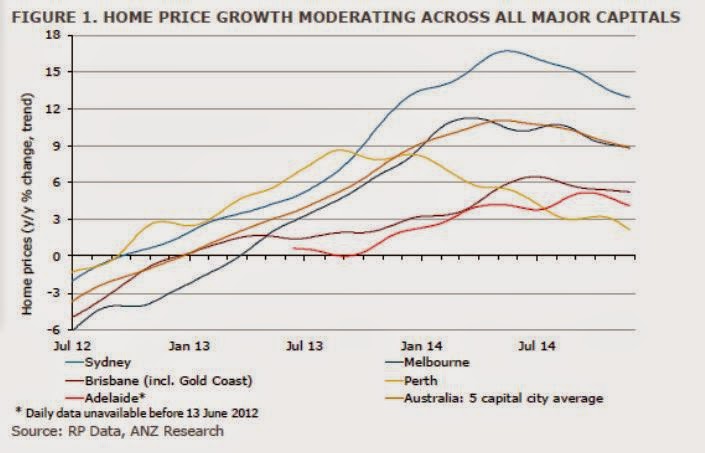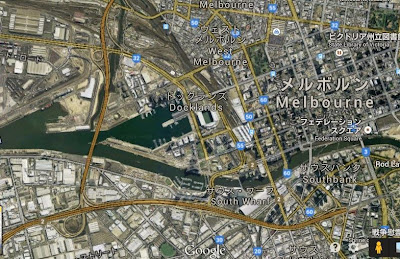週1、2回の掃除やゴミ捨てサービスが付帯している家具付きのマンションです。オーストラリアではServiced Apartmentと呼ばれています。
入居してすぐに生活を始められ、電気や水道などの利用申し込みも不要なため、現地に不慣れな人にとっては便利な居住形態です。
もっとも、公共料金込みで、サービスに付加価値が付いている分、自分でマンションを借りるのよりは割高です。それでも、フルサービスのホテルに泊まるのに比べれば、広い部屋に割安で滞在できます。
利用者は、比較的長く滞在する旅行者や、海外からの駐在員(途上国の場合)がほとんどです。
自分でマンションを借りるのに比べて割高になるため、地元の人は通常住んでいません。途上国に比べて治安や生活インフラの心配がない先進国では、駐在員でもこうしたタイプには住んでいないでしょう。
先進国の場合、借り手は旅行者、出張者になりますから、数日・週単位の契約など、基本的にテナント付けが不安定です。
また、都心に近いところでは、地元の人が住んでいるマンションの中に、一部、こうしたコンドミニアムとして短期滞在用に貸し出している部屋が混在しているケースもあります。
こうしたマンションに住んでいる知人がいますが、旅行者が多いため、(旅先で気分が高揚してか)夜遅くまで騒がしい、出入りしている人の素性が分からないなど、住民には評判が良くありません。
このため、自宅用に買いたいという地元の人の需要が少なくなります。オーストラリアの都市部では、住居購入者の6割が自宅用、4割が投資用ですが、後者の投資家しか売却の対象にできません。
さらに、投資家の中で、そもそもコンドミニアムを投資対象にしていない人は大勢います。
売却の対象が狭い上に、投資家は「価格を上積みしてでも、そこに住みたい」とは考えませんから、将来の値上がり(キャピタルゲイン)が狙いにくい物件となります。
また、地元の人があまり住まない、買わない物件となると、その地域の人口、GDPが成長しても、物件価格もそれに応じて伸びるとは限りません。
また、家賃収入に関しても、確かに取れる家賃額は通常のマンションより高いですが、短期滞在型の場合、ずっと満室ということはないこと、サービス運営会社のマネジメント料が通常の賃貸管理より高いことに注意が必要です。
また、観光産業に依存している地域の場合は、空室率や家賃が景気状況に大きく左右されます。景気が悪くなると旅行費が削られるためです。
都市部の駐在員滞在型の場合、家賃水準の関係で地元の人が借りられませんので、企業の進出・撤退状況に大きく左右されます。2008年のリーマンショックのころ、東京の六本木の高価格帯マンションが大苦戦したのと同じです。
投資対象国が先進国であれば、特定の産業に依存した地域で、あえてコンドミニアムを買う必要はないと考えます。
もちろん、自分が利用するためなら話は別ですが、この場合は、将来値段も上がればラッキーくらいの感覚で、投資と考えないほうがよいでしょう。
GDP、人口、物価が上昇している地域であれば、買った時よりも値段は上がるかもしれませんが、通常のマンションに投資する選択肢があるのなら、あえてコンドミニアムを狙う必要はないでしょう。
フィリピンなど途上国の場合は、まともな建物管理、賃貸管理ができ、ちゃんと家賃を払ってくれるテナントさんを見つけるには、駐在員対象のコンドミニアムくらいしかないこともあります。
現状、こうした国では、地元の経済的に余裕のある層は賃貸住宅になど住まないはずで、地元の賃貸マーケットが育ってくるには、長い時間がかかりそうです。
この場合は、コンドミニアムで将来の大化けに賭けてみるという手もあるかもしれません。
もっとも、現地の価格、家賃相場をしっかり把握したうえで、信頼できる賃貸管理の現地パートナーがいればということですが。特に後者が重要ですね。
ギャンブル性が高いということは認識したうえで、ポートフォリオの一つとして組み込むのは筆者も面白いと考えています。
株式投資で言えば、安定した大型株に、成長が期待される小型株、新興株を組み合わせる感覚です。もっとも、現地の都市開発や商慣習などの事情に詳しい方は別として、国内での不動産投資の経験もなく、途上国の物件に大きく賭けるのはお勧めできません。
人口、GDPの伸びが見込めるといっても、自分が購入した建物の耐久性能、管理・運営状況など個別のリスクもあるからです。
途上国の場合、街づくり自体も浮動的ですから、自分が購入した地区が10年後、20年後にどのような姿になっているか、見通しも大切です。
都市の成長に伴い、今の一等地が超一等地に、二等地が一等地に化ける可能性も秘めていることが面白いところでもあります。
もっとも、二等地は20年経っても二等地のままということもよくありますので、単なる「安物買い」にならないように都市開発の見極めが必要です。
例えば、万国共通で地区の価値を大きく変えるのは、電車の駅の新設です。街の規模が拡大するに従い、道路は渋滞し、都心部の駐車料金も高くなり、自動車での通勤が難しくなります。
シドニーやロンドンでは、中心部に車で乗り入れるだけで通行料金がかかります。このため、通勤に電車が使える地区の価値が高まってくるのです。